当社の製造品目に関する食材のうち、次のものについて解説しています。
昆布(こぶ)
海草類は、タンパク質、ビタミン類、ミネラル、カルシウムなどをバランス良く含むほか、新陳代謝・ホルモン生成に欠かせないヨードを多く含みます。ヨードは海草類からしか摂取できない栄養素です。
昆布の特徴として水に漬けると現れる「ぬめり」がありますが、これは水溶性の食物繊維の一種、アルギン酸によるもので、体内の余分なコレステロールやナトリウムを排出する働きを持っている為、直腸ガン、動脈硬化の予防にもなります。このアルギン酸は、胃や腸では吸収されず、腸の中をきれいに掃除しながら排出される為、便秘を解消するだけでなく、有害物質が長く腸に留まるのを防いで、大腸がんのリスクを減らす作用もあります。
また、塩分を体外へと排出するカリウムも多く含み、高血圧や動脈硬化などの成人病の改善に効果のある食品であります。
さらに、海草類の中で最も多くのヨードを含んでいます。前述の通り、ヨードは海草類からしか摂取できない成分で、新陳代謝を活発にし、血管の老化を防ぎ、抵抗力を高める働きを持ちます。特に育ち盛りの子供やお年寄りに不可欠の成分であります。さらにヨードは、甲状腺ホルモンを作りだす為、甲状腺に障害を持つ人が昆布を食べる事は症状の改善につながるとされています。
昆布は他にカルシウムやビタミンB1に富んでいます。多量のカルシウムは、丈夫な骨や歯を作る素となり、苛立った神経を鎮める働きを持ちます。
昆布に含まれるラミニンという血圧降下作用が認められるアミノ酸は、甲状腺腫、高血圧、老化を防止する効果があります。
| 効能: |
便秘解消
大腸ガン・動脈硬化・高血圧・貧血・老化・視力低下の予防
体力回復
精神安定
骨の強化
甲状腺障害
|
鰊(にしん)
にしんのビタミンB12含有量は魚介類の中でもトップクラスです。牛や豚のレバーにも多く含まれていますが、反面、コレステロールの含有量が多いので、コレステロールの気になる人は魚介類からの摂取のほうが望ましいと思われます。
ビタミンB12は、不足すると悪性貧血症になると言われており、その結果、不妊症を引き起こすとも言われています。また、不足してもすぐに症状が出ず、5年後くらいに影響が出ると言われます。また、神経疾患や糖尿病の治療薬にも用いられ、ボケ防止にも期待が集っています。
また、にしんはビタミンEの含有量がかなり高く、老化防止、性的機能の衰えや、精子の障害の予防にも有効です。ビタミンEは、抗酸化作用を持っている為、細胞が過酸化状態になって機能が損なわれるのを予防する役目も持っています。
いわしに次いで多く含まれるセレンもビタミンEと共に老化の進行を穏やかにし、体を若若しく保つミネラルで、動脈硬化や肝臓病、白内障などの病気の発生誘因になる過酸化脂質の生成を防ぐ働きがあると言われ、注目されています。
にしんはとりわけ脂肪が豊富で、動脈硬化の予防、血栓症に有効なEPA(エイコサペンタエン酸)や、脳の働きを良くするDHA(ドコサヘキサエン酸)がたっぷりと含まれています。このDHAには、アレルギー性皮膚炎を引き起こすヒスタミンやロイコトリエンを減らす役目もあります。
マグネシウムや銅、亜鉛などの微量元素も適度に含まれている為、体調を整えるのに適した食品であります。
| 効能: |
老化防止
性的機能の衰え
精子の障害の予防
脳の活性化
血栓症
アレルギー性皮膚炎
|
鮭(さけ)
鮭の栄養的特徴は、タンパク質と脂肪を多く含んでいる事。特に、脂肪には、悪玉コレステロールを減らして動脈硬化などを予防するEPA(エイコサペンタエン酸)と、脳の働きを良くするDHA(ドコサヘキサエン酸)が豊富に含まれています。
また、ビタミンA、B1、B2、D、Eをはじめ、B6も多く含んでいる為、他の魚に比べてタンパク質の吸収、消化が良いと言われています。
魚類の中で鮭に特に豊富に含まれるビタミンAは、風邪の予防や皮膚障害に有効な成分です。
鮭の卵であるイクラや筋子には「若返りのビタミン」と言われるビタミンEが多く含まれており、老化防止や美肌、性的能力の維持に必要な栄養素であります。
中骨には、ビタミンDが多く含まれ、骨軟化症の予防に効果があります。
鮭は胃腸を温めて血液の巡りを促してくれる為、胃弱や冷え性の人にも適しています。
| 効能: |
体力回復
動脈硬化・骨軟化症・骨粗鬆症・高血圧・風邪・冷え性・老化の予防
不眠症の改善
|
鰻(うなぎ)
うなぎは魚貝類の中でも栄養価が高い食品で、脂肪は本マグロに匹敵するほどであります。また、血中のコレステロール値を抑制する作用があるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)も多く含んでいます。コレステロールを抑える作用がある反面、100g中に200mgものコレステロールを含んでいますので、食べ過ぎは禁物で、野菜や海草などの食物繊維を多く含む食品と一緒に摂取する事により、体外に排出する効果が得られます。
また、うなぎはビタミンが豊富で、特に豊富に含まれているビタミンEは、「若返りのビタミン」と言われ、年齢と共に体内に増えてくる老化促進物質の一つである過酸化脂質の増加を抑える働きを持ちます。更に末梢血管を開き、全身に血液を送りこみ易くして、全身を生き生きさせます。
うなぎの蒲焼や白焼き100g中に含まれるビタミンAは、成人男子の1日に必要な摂取量の2〜2.5倍の5,000IUも含まれており、一般の魚に含まれる量の約50倍に相当します。ビタミンAは、不足すると視力障害を起こしやすく、骨や歯の発育にも悪影響があり、皮膚や粘膜の抵抗力も衰え、風邪をひきやすくなります。
うなぎの皮にはビタミンB1、B2も含まれている為、口内炎口角炎ストレスを予防するばかりでなく、成長期には欠かせない発育に必要な栄養素となります。また、カリウムの効果で高血圧の予防にもなります。
| 効能: |
夏バテ解消
体力回復
風邪・視力低下・皮膚障害・味覚障害・脳卒中の予防
口内炎・口角炎・ストレス・高血圧の予防
|
真鱈(まだら)
底魚のたらは、タンパク質や脂肪はそれほどありません。しかし、魚肉ではビタミンDが多く、カルシウムやリンの働きを助け健康な骨や歯づくりに役立ちます。
また、ビタミンAを多く含む事により、美肌効果を高めたり、鼻やのどの粘膜を強くする働きがある為、風邪に対する抵抗力をつける事が出来ます。
| 効能: |
視力低下・骨軟化症・骨粗鬆症・風邪・老化の予防
美肌
|
牡蠣(かき)
牡蠣は、世界中で食されるとても栄養価の高い貝類です。(「海のミルク」と呼ばれています。)
一般の貝類がそうであるように、牡蠣にもアミノ酸の一種タウリンが多く含まれています。タウリンには、血圧や血中のコレステロール値を下げる効果があり、高血圧症や、動脈硬化の防止に役立つとされています。また、ビタミンB12も豊富に含まれており、肝臓機能の働きを高める働きも有ります。ビタミンB12は、悪性貧血を予防する働きも持っています。
貧血の予防には、鉄、銅は欠かせません。(貧血の90%が、鉄欠乏性貧血と言われています。)牡蠣には、この鉄、銅が含まれていますので、若い女性に多く見られる鉄欠乏性貧血の予防に最適な食品です。
亜鉛不足は、子供の成長に影響します。牡蠣は、亜鉛の含有量が高く、2粒で1日の必要量を得る事が出来ます。亜鉛は、筋肉や骨、肝臓などに多く分布していますが、男性の場合では「前立腺」にも結構存在しています。前立腺で、性ホルモンの合成に関わっているからで、亜鉛不足は、思春期では性成熟が遅れ、成人では生殖能力が衰えて子供が出来難くなります。
| 効能: |
動脈硬化・高血圧症・視力低下・貧血の予防
肝臓機能の働きを高める。
子供の成長を促進。
味覚障害や性機能の改善。
|
Back to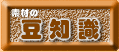 Page.
Page.
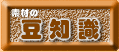
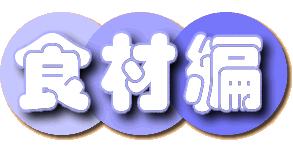
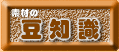
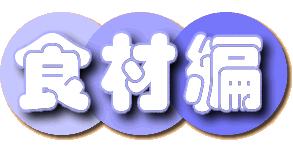
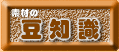 Page.
Page.