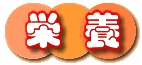 |
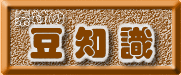 |
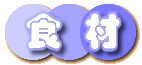
|
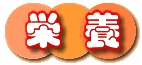 |
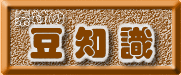 |
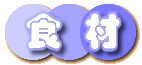
|
| リン |
[特徴] 体重の約1%を占めるリンは、生体内では炭素、窒素、カルシウムに次いで多い元素です。 リンの80%は、カルシウムと結合し、骨や歯の成分(リン酸カルシウム、ハイドロキシアパタイト)となっています。また、残りは筋肉、脳、神経、肝臓などあらゆる組織にあり、重要な役割を担っています。 日本人の食生活では通常、不足する事は無く、むしろ過剰に摂取しています。というのも、リンは多くの食品に含まれており、加工食品や清涼飲料水には、保存の目的で、ポリリン酸が添加されている事が挙げられます。 リンとカルシウムの理想のバランスは、「1:1」です。しかし、日本人のリンの摂取量は1,300mg程度という報告があり、カルシウムの所要量(600mg)を満たしていない日本人の食生活では、過剰に摂取しているのが現状です。 リンとカルシウムは同じ食品に含まれる事が多い為、カルシウムを多く含む食品を心掛けてとる事が、理想のバランスに近づく事になります。 [効能・効果] 脳を造る。(リン脂質) 丈夫な骨を造る。 強い歯や歯ぐきを造る。 細胞膜を構成し、細胞の成長や分化に働きます。 ビタミンB1、B2と結合して補酵素となり、糖質の代謝に働きます。 高エネルギーのリン酸化合物となり、エネルギーを蓄えます。(ATP:アデノシン三リン酸) [欠乏症] 歯と歯ぐきが弱くなる。歯槽膿漏になり易くなります。 新陳代謝が低下して、筋肉の力が弱くなったり、だるくなります。 神経痛を起こしやすくなる。 腎臓に結石が出来易くなります。 子供では、発育が遅れたり、くる病になります。 [過剰症] 副甲状腺機能亢進 甲状腺の裏側上下左右に合計4つある、直径3〜5mmの小さな臓器が副甲状腺です。ここからカルシウムの代謝を調節するホルモンを分泌していますが、副甲状腺の1つが腫れて、副甲状腺ホルモンを大量に分泌するようになる病気を副甲状腺機能亢進または、副甲状腺腺腫といいます。この副甲状腺機能亢進には、大きく分けて3つのタイプがあり、「骨型」「腎結石型」「科学型」に分けられます。 「骨型」は、骨のカルシウムが減少し、骨粗鬆症を引き起こします。 「腎結石型」は、その名の通り、腎臓に結石が出来ます。 「科学型」は、血液中のカルシウム値が高いだけであまり症状は出ませんが、イライラや頭痛などの神経障害、胃炎や胃潰瘍などの消化器へ症状が現れる場合があります。 この病気は放っておくと血中のカルシウム値が高くなりすぎる事により、「副甲状腺クリーゼ」と呼ばれるショック症状を起こすことがあります。 骨代謝障害 [1食あたりに含まれる量] ※リンを多く含みカルシウムとのバランスが1:1前後のものです。
※1日の適正摂取量 成人:600mg [POINT] 肉類、魚介類、乳製品は、リンの含有量が多いです。 魚介類、乳製品は、カルシウムの含有量も多いので、バランスは良いですが、肉類はリンの含有量が多いので注意しましょう。 豚もも肉100g中では、カルシウムが5mg、リンが200mgというバランスですので、肉食中心の人は過剰摂取に気を付けて下さい。 ※骨粗鬆症や腎臓の悪い方は特に気を付けて下さい。 |